ロコモティブシンドロームってなに?
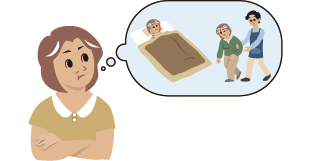
人間が立つ、歩く、作業するといった、広い意味での運動のために必要な身体の仕組み全体を運動器といいます。運動器は骨・関節・筋肉・神経などで成り立っていますが、これらの組織の障害によって立ったり歩いたりするための身体能力(移動機能)が低下した状態が、ロコモです。ロコモが進行すると、将来介護が必要になるリスクが高くなります1)。
現在日本では、「要支援」や「要介護」が必要とされる人の数は年々増えており、その約4人に1人は運動器の障害が原因です1)。そこで、健康でイキイキした生活を送るためには、「動ける能力(ロコモティブ)」を維持することが重要と考え、日本整形外科学会が2007年から「ロコモティブシンドローム」という言葉を提唱し、対策を呼びかけています。

体を動かすために、運動器は互いに関連し合って働いています。このため、運動器のどれか一つが衰えたり病気になったりすると、体をうまく動かすことができなくなり、転倒などの危険が高まってしまいます。そして、「要介護」や「寝たきり」になってしまうおそれがあります。
そうなる前に、腰やひざの痛み、加齢によるバランス能力や筋力の低下などの症状が現れた早い段階から「ロコモティブシンドローム」としてとらえ、対策を行うことが重要です。
ロコモの要因は、運動器の病気、運動器の能力の衰え、運動器の痛みなどさまざま。これらの要因がつながったり、合わさったりすることでロコモになり、進行すると社会参加・生活活動が制限され、ついには要介護状態に至ってしまいます。ロコモと判定された場合、原因は何かを見極め、状態に合わせて適切に対処することが必要です。
対処法には病気の予防、病気に対する薬物や手術による治療、運動器の力の衰えに対する筋力やバランス力のトレーニング、痛みや痺れに対する治療、栄養不足や栄養過多の改善などがあります。また生活習慣病の予防やその治療を合わせて行うことも必要です。
ロコモは回復可能なのが最大の特徴。きちんと対処すれば、不安や不自由なく歩けるようになります1)。
日本整形外科学会では、7項目の「ロコチェック」を提唱し、一つでもあてはまれば「ロコモティブシンドローム」を疑い、整形外科専門医を早い段階で受診するようすすめています。
●7つのロコチェック
- 片脚立ちで靴下がはけない
- 家の中でつまずいたり滑ったりする
- 階段を上るのに手すりが必要である
- 家の中のやや思い仕事(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)が困難である
- 2kg程度の買い物(1リットルの牛乳パック2個程度)をして持ち帰るのが困難である
- 15分くらい続けて歩けない
- 横断歩道を青信号で渡りきれない
ロコチェック ロコモ ONLINE 日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイトより
また、ロコモティブシンドロームが疑われる場合には、転倒や骨折を予防するためのロコモーショントレーニング、略して「ロコトレ」を行いましょう。
1) 日本整形外科学会:ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモオンライン
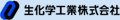
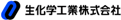

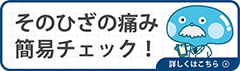
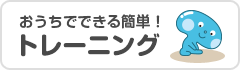

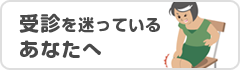


 ヒアルンくんに学ぶ!
ヒアルンくんに学ぶ! ロコモティブ
ロコモティブ ひざの痛みと生活習慣病
ひざの痛みと生活習慣病 「ひざの痛みに関する
「ひざの痛みに関する フレイルってなに?
フレイルってなに? 動画で解説する
動画で解説する